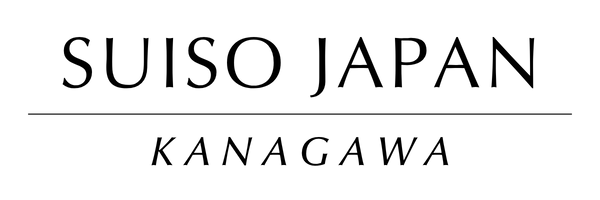
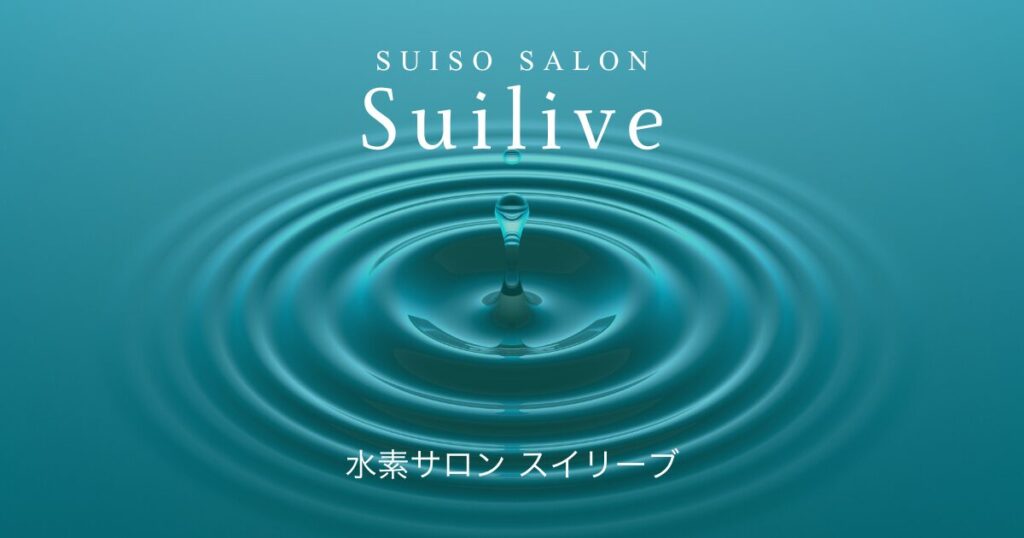
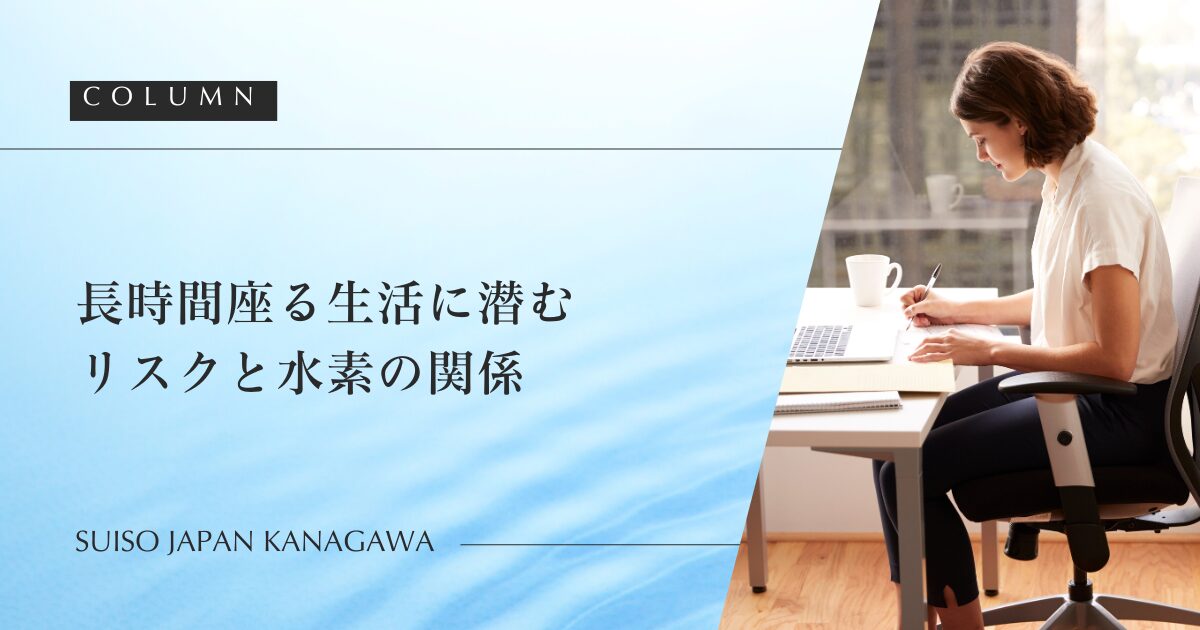
パソコン作業、会議、移動、食事、スマホ…。
日々の生活を振り返ると、私たちは思っている以上に「座っている時間」が長くなっています。
便利な現代社会に欠かせないこの座りっぱなしの習慣は、実は健康リスクの温床であることが、近年あらためて問題視されています。
その中で、水素を活用した疲労回復が注目されているのは、リラックス効果だけにとどまらず、座り続けることによって生じる体内の変化に、根本からアプローチできる手段だからです。
世界保健機関(WHO)も警鐘を鳴らす「座りすぎ症候群」。
海外では「Sitting is the new smoking(座りすぎは新たな喫煙)」とすら言われています。
長時間座りっぱなしの生活が続くことで起こる主なリスクは以下の通りです:
つまり、座りすぎとは単なる姿勢の問題ではなく、血流と代謝の低下を中心に全身の機能が鈍ることにほかなりません。
長時間の着座姿勢では、筋肉の活動がほぼ止まることで、血液やリンパの循環が極端に悪化します。
その結果、筋肉や内臓、脳などの各所で酸素不足が発生し、悪玉活性酸素が増加。
これが細胞を酸化させ、いわゆる静かな炎症(サイレントインフラメーション)を招くと考えられています。
この状態が慢性化すると、だるさ・疲れ・集中力の低下・情緒の不安定さといった、目に見えにくい不調が日常化してしまいます。
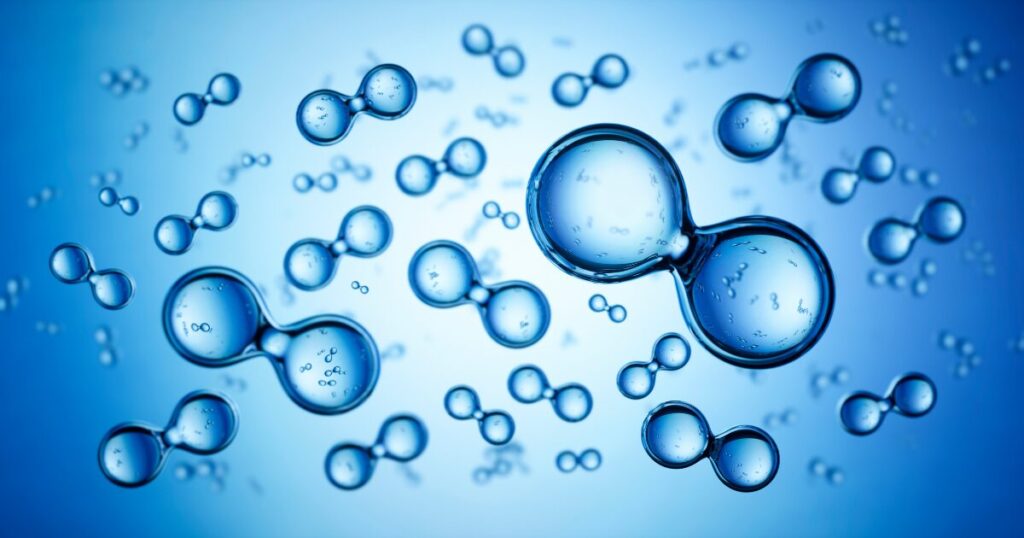
水素は、この静かに進行する酸化ストレスに対し、選択的にアプローチできる抗酸化作用を持っています。
特に、ヒドロキシラジカルという最も攻撃性の高い悪玉活性酸素と結びつき、無害な水として排出できる性質が特徴です。
また、水素吸入によって副交感神経が優位になり、全身の血流が促進されることも報告されています。
つまり、座っていることで停滞した体内の“流れ”を整える手段として、水素は有効に働く可能性があるのです。

水素吸入は、すでに不調が出てからではなく、不調が出る前の「リセット」の手段としても活用できます。
たとえば:
これらはすべて、負担の少ないながらケアとして生活に組み込める方法です。
動かずにいることは、身体にも心にも確実に影響を与えます。
たとえ1日10分でも、自分の内側に「流れ」を取り戻す時間を設けることは、新しい健康習慣と言えるかもしれません。
水素吸入は、座ることで生まれるリスクに対して、静かに、しかし確実に働きかけてくれます。
日々の中に水素を取り入れる時間を取り入れることが、明日の集中力と体調を守る第一歩になるはずです。
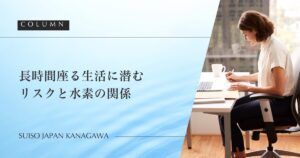
この記事が気に入ったら
フォローしてね!